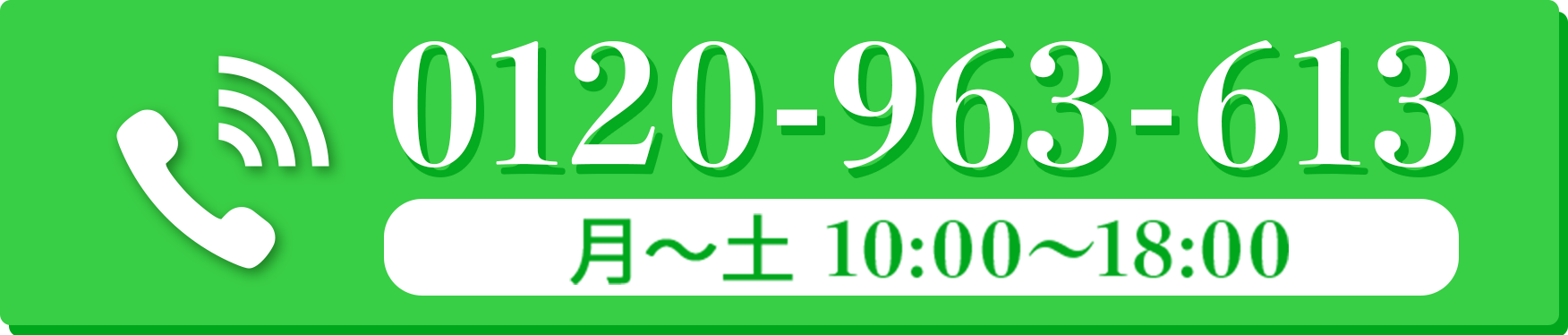Q 亡母が残した公正証書遺言により、兄が相続財産のほとんどを取得することになりました。このような遺言があったとしても、「遺留分」というものを主張できると聞いたことがあるのですが、遺留分の請求はどのように行うのがよいでしょうか。またその効果はどうなりますか。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談のケースは、相続人である子の遺留分を侵害するような遺言があるため、遺留分を侵害しているとして、遺留分減殺請求を行うことを希望しているものです。
遺留分に関するご相談は、多数の相続のご相談が寄せられる弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所千葉事務所においても大きな比重を占めている分野といえます。
遺留分は複雑な計算を行う必要があり、遺留分の計算方法、基礎となる相続財産の調査、収集方法など、相続の専門家である弁護士が大きな力になる相続分野といえます。
遺留分減殺請求の方法は、決められた書式などはありませんが、後日、紛争になった時に備え、書面にて行うことがよいでしょう。また、弁護士としては、遺留分侵害者へ遺留分減殺の意思表示の到達が争われることがあるため、内容証明及び配達記録で行うことをお勧めします。
遺留分減殺に関する書面が相手方に到達すれば、遺留分減殺の効力が生じます。その後は、どの財産で遺留分の支払いを行うのかについて、相手方と交渉または裁判(遺留分減殺の調停または訴訟)を行います。
弁護士による相続解説:遺留分減殺請求は、口頭でも可能ですが、証拠化のためにも「書面で行う」ことがよいでしょう(意思表示をしたという証拠化のためのものなので必ずしも内容証明である必要はありません)。
遺留分減殺請求は、1年の消滅時効あるため注意が必要です。消滅時効の期間の起算点について、疑問があれば、速やかに弁護士へ相談を行ってください。
遺留分減殺請求権の効果は,理論的には請求により遺贈・贈与された財産の一定割合が遺留分権利者に当然に帰属することになります(民法1041条)。
もっとも、遺留分を侵害しているものが任意に財産の引き渡しを行わない場合には、別途、裁判手続きなどを検討する必要があります。
遺留分に関する事柄は、遺言の有効性、相続財産の調査、その評価など専門的な事柄を多く含みますので、相続の専門家である弁護士へご相談することをお勧めします。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)